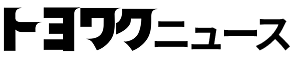トヨタNews

豊田章男は創業家の精神を守りながら、トヨタの未来を見据えている
2025年4月、アメリカの自動車専門紙『オートモーティブ・ニュース』に豊田章男会長のインタビューが掲載された。
1925年に創刊した同紙は、デトロイトに本社を置き、全米だけでなく欧州や日本など世界各地からニュースを届けている。
今回のインタビューは、同紙の創刊100周年を記念して実施。豊田佐吉翁から始まる豊田家を「自動車産業に対し、ビジョンや革新性、リーダーシップにより継続的な影響を与えた」として特集された。
この1925年という年は、トヨタにとっても重要な年だ。
同年は、トヨタが織機からクルマへと事業をモデルチェンジするための資金を生み出した、G型自動織機の量産が始まった年。章一郎名誉会長が生まれたのも、この時期だ。
100年前に始まったオートモーティブニュースと、100年前にクルマ屋へ舵を切るきっかけを得たトヨタ。
インタビューの中で豊田会長は、「ゲームチェンジが起こった年」と語っている。トヨタイムズでは今回、豊田会長のコメントも収録したオートモーティブニュース記事を特別に掲載する。
【ここからオートモーティブニュース】
豊田章男会⾧によると、1925年はオートモーティブニュース(AMN)と同様に、トヨタ自動車にとっても、特別な年だった。この世界最大の自動車メーカーは、当時は自動車産業に参入さえしていなかった。しかしこの年に、豊田家の先人達が創設した会社が、画期的発明であるG型自動織機の大量生産を始めたことで、歴史の流れを変えた。
オートモーティブニュース100周年を記念したロゴ
G型自動織機の大成功は、世界でもっとも成功した企業の一社であるトヨタの始まりとなり、豊田家の功績が、産業史に刻まれることを確固たるものとした。
1925年はまた、AMNが創刊された年でもある。AMNは過去100年間を振り返り、豊田章男と、彼から4代さかのぼるその一族の⾧年に渡る卓越した功績に敬意を表し、100周年記念賞を授与している。
「1925年はオートモーティブニュースだけでなく、トヨタ自動車にとっても特別な年でした。非常に大きな意味のある、おそらくゲームチェンジが起こった年だったのです」。章男氏はこう語った。トヨタの社⾧、会⾧を⾧く務めた父の章一郎氏が生まれたのもこの年だったという。
G型織機の売上は、豊田家が当時黎明期だった自動車業界に踏み出すための強固な財務基盤を作り上げた。その影響は非常に大きく、トヨタは復元した自動織機を東京オフィスの役員室のロビーに誇らしげに展示している。その隣には、トヨタが開発した最初の自動車、AA型乗用車のレプリカが飾られている。
章男氏は「この織機の大量生産は1925年に始まりました」と、織機の前で身振りをまじえながら語った。「当時米国では、自動車は大衆のものになっており、年間300万台が生産されて路上を走っていた。しかし自動車会社としてのトヨタは、存在すらしていなかったのです」。
この影響力のある巨大な企業グループは、日本の経済大国への成長を牽引しただけではない。そのグループから生まれた代表的企業であるトヨタ自動車は、世界の自動車業界の姿を一変させた。
章男氏は、3月25日に行われた受賞にあたっての取材で、トヨタの卓越した歴史を振り返りつつ、そのはじまりを曾祖父である豊田佐吉に求めた。
豊田佐吉の原動力は、自分以外の誰かのためにという想いだった
佐吉の若い頃、近代日本はサムライの時代から世界に目を向け始めて間もない時だった。⾧らく鎖国していたこの島国は、西欧列強の技術力と商業力に包囲されているように見えた。質素な大工の家に生まれた佐吉は小学校での教育しか受けていないが、当時の状況を見据え、国を助けたいとの想いに駆られていた。
章男氏は、佐吉が他の誰かの仕事の負担を減らすことで、社会に貢献できるということを見出したと、誇りを持って語っている。大工仕事や農作業を手伝い、夜に帰宅すると織物を行っていた佐吉の母を助けることが始まりだったという。
「佐吉は、母親の生活を楽にしたかったのです」と章男氏は語る。「佐吉のこうした考えは、おそらくトヨタの原点だったのだと思います」。
佐吉の問題解決への欲求は、世界初の無停止シャトル交換機構を持つG型自動織機の開発につながった。革新的な設計により、作業者の負担が軽減されただけでなく、作業効率も数倍向上した。
トヨタに入社した際は歓迎されていないと感じたと語る豊田章男会⾧。価値を証明するため、懸命に働かないとならなかったという。(トヨタ自動車提供)
章男氏は、同じ精神がトヨタ自動車を導いていると説明する。そしてその精神こそ、AMNが豊田家に100周年賞を授与した理由でもある。この賞は、自動車業界の擁護者、批評者としてのAMNの100周年を記念するものだ。そして、世界でもっとも刺激的なビジネスである自動車産業に対し、ビジョンや革新性、リーダーシップにより継続的な影響を与えた卓越した個人、家族に贈られるものだ。
豊田家は株式の保有でなく、創業家の精神で社を導く
佐吉以降の3世代も、トヨタを導いた。章男氏の祖父、喜一郎は1937年、佐吉がつくった豊田自動織機からの分離独立の形で、トヨタ自動車工業を設立。父の章一郎氏は、1981年から92年までトヨタ自動車の社⾧を、92年から99年まで会⾧を務めた。章男氏は2009年に社⾧に就任し、23年からは会⾧を務めている。佐吉の甥である豊田英二は1967年から81年まで、章一郎氏の弟の豊田達郎氏も92年から95年まで、それぞれ社⾧を務めている。
今日、トヨタ車は世界のあらゆる場所で販売されている。トヨタブランドは品質と信頼性の代名詞で、豊田家のリーダー達が切り開いた事業の手法は、製造業の教科書を塗り替え、リーン生産方式やカイゼンが紹介されるようになった。創設から約90年が経過し、トヨタは世界最大の自動車メーカーとなり、なおかつ利益率でも最高の水準にある。
豊田章男会⾧は創業家3代目の経営者であり、息子の大輔氏もトヨタに入社した。(トヨタ自動車提供)
世界中でトヨタは数十万人を直接雇っている。そしてその何倍もの雇用を、サプライヤーやディーラー、関連会社で生み出している。
創業家3代目としての重圧は、68歳の章男氏に重くのしかかっている。「日本では、3代目は会社をさらに発展させるか、潰すかのどちらかだと言われているんです」と語る章男氏。「私はこの会社への投資家でもなければ、投資の貢献者でもありません。社内には、私がトップにいることを快く思わない人もいました」という。
トヨタでトップに上り詰めるまでの苦難
実際、章男氏が社内で昇格していった際は、懐疑論者が多かった。豊田家の家名はクルマに冠されているが、一家の株式保有比率は、世代が下るにつれ象徴的にすぎない水準にまで減っている。章男氏は、自身の価値を証明するために、2倍働かなければならなかったと振り返る。
「トヨタに入社したときは、あまり会社に歓迎されていませんでした。今もここにいられるのは、いつかは会社に必要な人材になれるよう努力して毎日を過ごしていたからというだけです。自社だけでなく、いつかは自動車業界にとっても必要な人物と言われるよう、努力をしてきました」
トヨタ東京オフィスでインタビューに答える豊田章男会⾧(3月25日)。G型自動織機の動作を説明している。(トヨタ自動車提供)
章男氏が最終的には家名の重みを悟ったのは、意図せぬ急加速によるリコール問題を謝罪するため、米国の議会で証言に立った時だった。
「社⾧になってすぐ議会証言を行い、『すべてのクルマに私の名前がついている』と言ったのは、話したのが私だったから意味があったのだと思います」と章男氏は語った。「会社を経営していると、良いときも悪いときもあります。しかし重要なのは、何を言ったのではなく、誰が言ったかなのです。それには、物事を動かす力があります」。
トヨタの外でも、章男氏はモータースポーツやテクノロジー、安定的な雇用まで、自動車に関するあらゆるもののリーダーとして、違いを生み出すという使命を担っている。章男氏は、日本自動車工業会の会⾧として前例のない3期を務め、激動の10年間を通じて、世界最大級の業界の舵取りを務めた。
豊田大輔氏が創業家のバトンを未来に引き継ぐ可能性は
章男氏が社⾧に就任したのは、世界的な金融危機を受け、トヨタが71年間の歴史の中で初めて営業赤字を計上した時だった。当初の数年は、章男氏が辞任を考えた、リコール問題や2011年の東日本大震災と福島第一原発事故により、荒波は激しさをさらに増していった。しかし、トヨタの基本原則に基づいた倫理に集中することで、章男氏はトヨタを新たな高みに導いた。
トヨタの「マスタードライバー」として、章男氏はあらゆるクルマのハンドリングの味付けにかかわっている。そして、彼の「もっといいクルマ」へのこだわりは、かつては退屈だったラインナップを、エキサイティングでスタイリッシュなものに変えた。章男氏は、トヨタを世界最大の自動車メーカーに育て上げ、過去最高の販売台数、利益、生産を達成した状態で、社⾧のポストを佐藤恒治氏に引き継いだ。
ただ、章男氏は、⾧い歴史を持つ創業家の系譜にある。代わりの利かない日本経済の柱、模範となる企業市民、世界のあらゆる場所でビジネスを行う「町いちばんの企業」としてのトヨタをつくりあげたのは豊田家だった。
章男氏は、その系譜の最後の一人ではない。息子の大輔氏も、一家の使命に気を配っている。37歳の大輔氏は、トヨタに2016年に入社。現在は、ソフトウェアや未来のモビリティ事業を手がける子会社、ウーブン・バイ・トヨタのシニアバイスプレジデントを務めている。
この豊田家の4代目は、富士山のふもとで構想が進む、将来技術のテストを行うための都市「ウーブン・シティ」プロジェクトを監督する立場にある。
大輔氏は、父親のスピードへのこだわりを共有しているという。トヨタのレースチームで競技に参加し、モータースポーツ部門であるガズーレーシングのテストドライバーも務めている。
ただ、章男氏は、息子が自身の足跡をたどるかについては慎重だ。「彼は私の息子ですが、まったく別の人間です。彼には彼固有の人生があります。だから、彼に私が経験したような訓練をさせようとは思いません」。
一方で、章男氏は大輔氏に一つだけ引き継いでほしい役割もあると付け加えた。「それは、マスタードライバーです。ブランドを持つメーカーとして、マスタードライバーはブランドの味付けを決める存在です。ブランドの味は時代によって変わるでしょう。トヨタの味、レクサスの味、GRの味などは、その時々で決定していく必要があります。だからいつか、彼がこの部分を受け継いでくれることを願っています」。
トップ画像説明
3月25日、トヨタ東京オフィスでG型織機の隣に立つ、トヨタの豊田章男会⾧。1925年にこの織機の大量生産が開始されたことが、トヨタの重要なターニングポイントになったと述べている。(撮影:ハンス・グライメル/オートモーティブニュース)※インタビューは、インタビュアーと通訳が英語で話し、豊田会長が日本語で答える形で行われています。
記事では描かれなかった一面も
オートモーティブニュースでは、会長との質疑をもとに記事を構成していたが、これとは別に、インタビューの様子を質疑応答の形でも掲載していた。ここでは、先ほどの記事には描かれなかった、豊田家とトヨタの関係やバッテリーEVへの想いも語っている。
【質疑応答記事はここから】大事なことは共感し合い、協力し合い、感謝し合うこと
トヨタ自動車の豊田章男会⾧は、アジア担当編集者のハンス・グライメル氏とのインタビューに応じ、豊田家を代表して「オートモーティブニュース100周年記念賞」を受賞した。2009年に自身の名を冠した自動車メーカーのトップに就任し、⾧年にわたり業界をリードしてきた章男氏は、創業家の功績や将来の役割、電動スポーツカーの予測まで、さまざまな話題について語った。
質疑の抜粋は以下の通り。
――豊田家の世界の自動車産業への貢献という意味で、重要なターニングポイントは何だったのでしょうか?
豊田会長
はじまりは、豊田佐吉が生まれた頃かもしれません。佐吉は私の曾祖父です。彼は大工の息子として生まれ、小学校しか出ていません。
佐吉の子供時代、欧米各国は急速に工業化していました。その様子を見て、もしかしたら日本が取り残されるのではないかと、彼は悩んでいたのです。
彼はまた、母親が家族を支えるために一生懸命働くのを見ていました。彼女は大工仕事と農作業で夫を支えながら日中ずっと働いていました。そして夜になっても、家で機織りをしていたんです。佐吉は、起きている間はずっと母が働いているのを見ていたということです。彼は母親の生活を楽にしたかったのです。
佐吉のそんな考え方が、トヨタの仕事の原点だったと思います。
――それがどう現在のトヨタにつながっているのでしょうか?
佐吉はそこから発明を始め、G型自動織機の誕生につながりました。量産が始まったのは1925年です。
その時米国ではすでに自動車が普及していて、約300万台の自動車が生産され、道路を走っていました。しかし、トヨタ自動車という会社も存在すらしていなかったのです。私の父、章一郎が生まれましたのもその年です。さらに、オートモーティブニュースの始まりの年でもあります。
これもゲームチェンジャーですよね? 1925年は、オートモーティブニュースだけでなく、トヨタ自動車にとっても特別な年だったと言えるでしょう。非常に重要な年であり、おそらくゲームチェンジャーの年だったでしょう。
――クルマの面ではどうでしょう?
1930年代後半には、自動織機事業から自動車事業への大きなモデルチェンジがありました。その移行は、私の祖父である豊田喜一郎とその後の世代が主導しました。これは私たちにとって2つ目のゲームチェンジであり、自動車会社への大きなモデルチェンジです。
――トヨタのリーダーとして、最大の課題は何でしたか?
トヨタに入社したときは、あまり歓迎されているとは感じませんでした。私がここにいるのは、いつか会社が必要と認める人間になれるように努力しながら、毎日を生き続けてきたからです。会社だけにとどまらず、いつか自動車業界にも「必要とされている人間だった」と言えるように努力してきました。
私は3代目です。日本では、3代目が会社をさらに発展させるか、倒産させるかのどちらかになるとよく言われます。
企業資本の相続を考えると、相続する資本は代を重ねるごとに減っていきます。ですから、3代目になる頃には、資本によるオーナーシップはほとんどありません。私は、この会社に対する投資家でも、資本面の貢献者でもありません。ですから、社内には、私がトップにいるのを快く思わない人もいました。
――豊田家は、どのように会社に関わっていくのでしょうか。
まず、我々は理念や会社の思想を共有しているかどうかを重視しています。そして、自動車業界で働くために、自動車ビジネスを行うために必要な技があります。さらに、トヨタの人間に期待される適切な所作があります。
この3つは社内から受け継がれてきたもので、私は成⾧していく中で様々な人から教育を受けてきました。ですから、トヨタが作り出した3つのこと、つまり思想、技、所作が私の武器になったのだと思います。
豊田家であることで唯一大切なことは、クルマにファミリーネームが刻まれていることです。私が社⾧になった直後に米国の議会の公聴会に行き、「すべてのクルマに私の名前がついている」と言った時、それは意味があったと思います。会社を経営していると、良い時とそうでない時があります。しかし、何を言うかよりも、誰が言うかが重要な局面があります。それが物を動かす力を持つことがあります。
大事なのは、豊田家かそうでないかではなく、全員の力を活かして、自動車業界とトヨタのために共感し合い、協力し合い、感謝し合うことです。家名を冠する将来の世代について、そして今この会社で働く私にとって考えると、我々豊田家の役割は、人々やステークホルダーに門戸を開くことであり、我々に話しかけてもらえれば、声が届くと感じてもらうことです。
大輔氏への想い
――息子の大輔氏は、どのように豊田家の功績を引き継いでいくのでしょうか?
彼は私の息子ですが、全く別の人間です。彼には彼自身のユニークな人生があります。
なので、私が経験したことで彼を訓練すべきではないと思います。私が身に付けたすべての技術を彼が身に付ける必要はないと思います。
実は、彼に受け継いでほしいと思うことが1つだけあります。それは、私がマスタードライバーであるという事実です。メーカーにとって、マスタードライバーはブランドの味を決める人です。今とは異なる味になる時代がおそらく来るでしょう。トヨタがどのような味を持つのか、レクサス、GRなどがどのような味を持つのかは常に判断する必要があります。だからいつか、この部分を受け継いでくれるといいなと思っています。
――あなたとどちらが優れたドライバーですか?
運転は大輔です。でも、クルマの味付けに関しては、まだ私が一歩先を進んでいるかなと思います。大輔のように若くしてスタートした人がどうなるのか楽しみです。私は師匠である成瀬(弘)さんに、50歳くらいの時に運転を教えていただきました。成瀬さんも、私がクルマの味付けについても知っていれば、きっとトヨタにとってもアドバンテージになるのではと見越していたと思います。
――米国の通商政策の変更は、トヨタの米国への新規投資を促すのでしょうか?
トヨタでは、どの国でも常に「町いちばん」の企業を目指しています。この方針の下で、米国内に10カ所以上の工場を設立し、継続的で安定的な投資に努めてきました。また、安定した雇用の創出も目指しています。これは今後も変わらないでしょう。
――業界がEVに傾く中、トヨタがハイブリッドを堅持する自信を持てたのはなぜでしょうか?
カーボンニュートラルという言葉が広まったとき、私たちは「敵は炭素」と言いました。CO2を減らすためには、今何ができるかに焦点を当てる必要があります。これが私たちの決定の土台です。この部分は当時から変わっていないですし、今後も変わりません。
これまでに販売したハイブリッド車は約2,700万台です。これらのクルマは、BEV900万台を走らせるのと同じCO2削減効果があります。
しかし、もし日本で900万台のBEVを作っていたら、実際にはCO2排出量を減らすどころか、増やしていたでしょう。それは、日本が電力を火力発電所に依存しているからです。
私たちはすべての選択肢を検討し、あらゆる方向で取り組むべきです。企業として、私たちは一貫して、敵は炭素であると言ってきました。
――トヨタがEVスポーツカーやレースカーを持つ日を想像できますか?
トヨタの中には、電動スポーツカーの開発に情熱を注ぐ人々が常にいます。しかし、マスタードライバーである私にとってのスポーツカーの定義は、ガソリンの匂いとエンジンの騒音があるものです。トヨタは量産ブランドですから、BEVでもアフォーダビリティ(トヨタイムズ編集部注:価格の手ごろさ)を考える必要があります。トヨタがBEVを手頃な価格で提供できるようになったら、その時がマスタードライバーである私がBEVスポーツカーを導入する瞬間かもしれません。
――また、マスタードライバーとして、EVを競技会でレースに出場させることはありますか?
ないです!ワクワクしないですね。なぜなら、1時間以上サーキットを走れないからです。
私がエントリーするのは耐久レースがほとんどなので、今のBEVではクルマのレースにはならないでしょう。充電時間やバッテリー交換などの競争になってしまいます。次のマスタードライバーはその挑戦をしなければならない。それは彼らの仕事です。
<関連リンク>