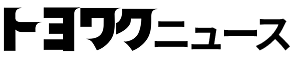トヨタNews

第22回 後編 試作と量産をつなぎ続けた「巻線の匠」永濵佳喜
3DプリンターやAIをはじめとするテクノロジーの進化に注目が集まる現代。だが、クルマづくりの現場では今もなお多数の「手仕事」が生かされている。
トヨタイムズでは、自動車業界を匠の技能で支える「職人」にスポットライトを当て、日本の「モノづくり」の真髄に迫る「日本のクルマづくりを支える職人たち」を特集する。
今回は、ハイブリッド車(HEV)や電気自動車(BEV)の動力源となるモーターのコイル開発を30年に渡って支えてきた、パワートレーン製造基盤技術部の永濵佳喜の後編をお届けする。
第22回 アジャイルな開発に貢献する「巻線の匠」永濵佳喜
トヨタ自動車 パワートレーン製造基盤技術部 工長
丸線から平角線へ、技術革新の波
2000年代に入ると、新たなモーター開発が始まった。サイズをコンパクト化させつつ高出力化を図り、コストも削減するという野心的な目標が立てられた。
その鍵を握ったのが、従来の丸線に代わって平角線を用いたSC(セグメントコンダクタ)巻き」と呼ばれる新技術だった。
従来のコイルに用いられた丸線 従来の丸線では、断面が円形のため、コイル同士の間に隙間ができる。この隙間は磁界の発生に寄与しない無駄なスペースだ。占積率(コイル配置空間に占める銅の割合)は40%程度だった。
平角線は断面が長方形で、隙間なく敷き詰めることができる。線積率は60%まで向上する。同じ体積でより多くの銅線を配置でき、より強い磁界を発生させられる。トヨタは業界に先駆けて、この平角線をハイブリッドモーターに採用した。
丸線に代わるコイルとして導入された平角線。金型でプレス成形してつくられる しかし、平角線は「巻く」のではなく「組み付ける」工程となった。直線状の銅線を型でプレス成形し、コの字型に曲げる。それを順番にステーターに挿入していく。
これにより生産効率は大幅に向上したが、永濵の役割も変化した。手巻きの機会は減り、平角線の工法開発が中心となった。金型や治具の製作、設備の調整。試作現場での新たな挑戦が始まった。
平角線を用いたステーター(上)と従来の丸線によるステーター。「巻く」から「組み付ける」へと作業も変化した 永濵
平角線を曲げたときの膨らみや傷がないかを確認します。図面に書いてある単品精度を保証するために、形状判定の方法も確立していきました。手巻きで培った知識は、ここでも活きた。どこに傷がつきやすいか。どうすれば銅線にストレスをかけずに成形できるか。永濵の経験が、平角線の工法開発を支えた。
2010年以降の試作開発は、平角線へと完全移行が進んだ。永濵は引き続き試作開発の中核を担っていたが、手巻きする機会は激減した。
この頃、技能伝承への懸念が、永濵の心に芽生え始めた。自分たちが何十年もかけて磨いてきた手巻き技能。それは本当に活かされるのだろうか。後進に伝える必要はあるのだろうか。
しかし、その答えは意外な形で訪れることになる。
SC巻き(左)では、ステーターからコイルがはみ出した部分も小さく抑えられるため、モーターのコンパクト化にも寄与する 10年ぶりの手巻き依頼
2020年、永濵のもとに東富士研究所から予想外の依頼が舞い込んだ。誘導モーター開発のための手巻きコイル製作だった。
誘導モーターは、HEVで使われる永久磁石同期モーターとは異なる構造を持つ。ローターに磁石を使わず、ステーターの回転磁界によってローター内に電流を誘導し、その電流が作る磁界で回転する仕組みだ。レアアースを使わないため、資源リスクを低減できる利点がある。
この誘導モーターの試作開発で、永濵の手巻き技能が求められた。10年のブランクがあった。しかし、実際に作業を始めると、身体が覚えていた。指先の感覚、道具の使い方、銅線の扱い方。30年間積み重ねてきた技能は、決して失われていなかった。
開発の柔軟性を生む手巻き技能
誘導モーターの開発では、設計者との密なやり取りが続いた。「コイルの巻き数を変えてみたい」「数多くの評価パターンをこの1台で熟せないか?」「完成納期を早められないか?」──設計者からの要望は次々と寄せられた。
通常、平角線は金型で成形するため、場合によっては仕様変更の際に金型を作り直す必要が生じる。開発初期段階で頻繁に仕様が変わる中では、時間もコストもかかりすぎる。
仕様変更に即座に対応できるのが手巻きの強みだと永濵は語る しかし、手巻きであれば柔軟に対応できる。永濵が手作業で条件を変えながら試作品を製作する。翌日には新しい仕様のコイルができあがる。
永濵
設計変更があっても、すぐに対応できます。これが手巻きの強みです。平角線では実現できない急な仕様変更にも、手巻きなら即座に応えられる。開発初期の試行錯誤の段階では、この柔軟性がアジャイルな開発にとって武器になる。
永濵が製作したコイルは、モーターの設計者に渡され、性能評価が行われる。データを見ながら、次の改良案が議論される。そしてまた永濵のもとに新しい仕様が届く。このサイクルを何度も繰り返すことで、最適な設計が見えてくる。この経験は技能員にとってもチャレンジと成長の機会に繋がっている。
永濵
試作の役割は、設計者が思い描くアイデアを素早く形にすることです。手巻きができると、開発の自由度が大きく広がります。平角線時代における手巻き技能の価値
平角線への移行は、モーター性能と生産性の飛躍的な向上をもたらした。しかし同時に、試作開発の柔軟性を制限する側面もあった。
従来の丸線を用いた(左)コイルとSC巻きによるコイル(右)、いずれにも精通している必要があると永濵は語る 誘導モーターの開発経験を通じて、永濵は改めて手巻き技能の価値を実感した。平角線での量産を見据えながらも、その前段階で手巻きによる試作を行う。このハイブリッドなアプローチが、効率的な開発を可能にする。
永濵は、手巻き技能と平角線技術の両方を理解しているからこそ、設計者と製造部門の橋渡し役を務められる。手巻きで確立した条件を、どうやって平角線の量産に落とし込むか。その知見が、スムーズな量産移行を支えている。
永濵
手巻きの経験があるから、平角線でどこに注意すべきかが分かります。銅線にストレスがかかる箇所、傷がつきやすいポイント。そういう知識は、平角線の工法開発にもつながります。技術が進化しても、手巻きで培った基本原理は変わらない。被膜を傷つけず、美しく整列させ、性能を最大限に引き出す。この本質は、どんな工法でも共通しているのだ。
技能伝承への取り組み
誘導モーターの開発を通じて、永濵は技能伝承の重要性を再認識した。
パワートレーン製造基盤技術部の後輩である蔵元亮二は、永濵の弟子として巻線技能の習得に尽力している 永濵
自分が引退したら、この技能は途絶えてしまうかもしれない。それでいいのだろうか。以前にも増して、そんなことを考えるようになりました。そこで、永濵は若手技能者の育成に力を入れ始めた。しかし、手巻き技能の伝承は容易ではない。
「見て覚えろ」という文化で育った永濵自身、言葉で技能を説明することの難しさを痛感していた。指先の力加減、道具の角度、銅線のヨリの調整。すべてが匠ならではのカンやコツの世界なのだ。
それでも、永濵は工夫を重ねた。まず、自分の作業を若手に見せる。そして実際にやらせてみる。失敗を恐れず、何度も繰り返させる。
永濵
最初はうまくいきません。それでいいんです。失敗から学ぶことが一番多いのですから。永濵自身、先輩の作業を見て学び、自分なりに工具を工夫しながら技能を習得してきた。その経験を、今度は次世代に伝えていく。
匠が見据える未来
永濵は今、50代を迎えた。定年まであと10年余り。技能伝承への取り組みを続けながらも、永濵自身の探究心は入社当時から変わっていない。より良いモーターを作りたい。その一心で、30年間技能を磨き続けてきた。
電動化の波は、今後さらに加速していく。BEVの普及が進み、モーターの需要は増え続ける。モーターの重要性が増す中、巻線技能の価値も再評価されている。
永濵
電動化は、まだ始まったばかりです。これから、もっと高性能なモーターが求められる。そのとき、自分の技能がどう活かせるか。楽しみです。伊根の漁師町で育った少年は、網目を編む文化の中で育ち、トヨタで銅線を巻く匠となった。RAV4 EVから初代プリウス、そして最新モーターまで。30年間、永濵が試作したコイルは、数え切れない。
手巻きから平角線へ。技術は変わっても、永濵が培った技能の本質は変わらない。設計者のアイデアを形にし、量産への道を拓く。電動化が加速する今、こうした試作現場の匠の技能は、これからも求められ続けることだろう。