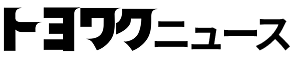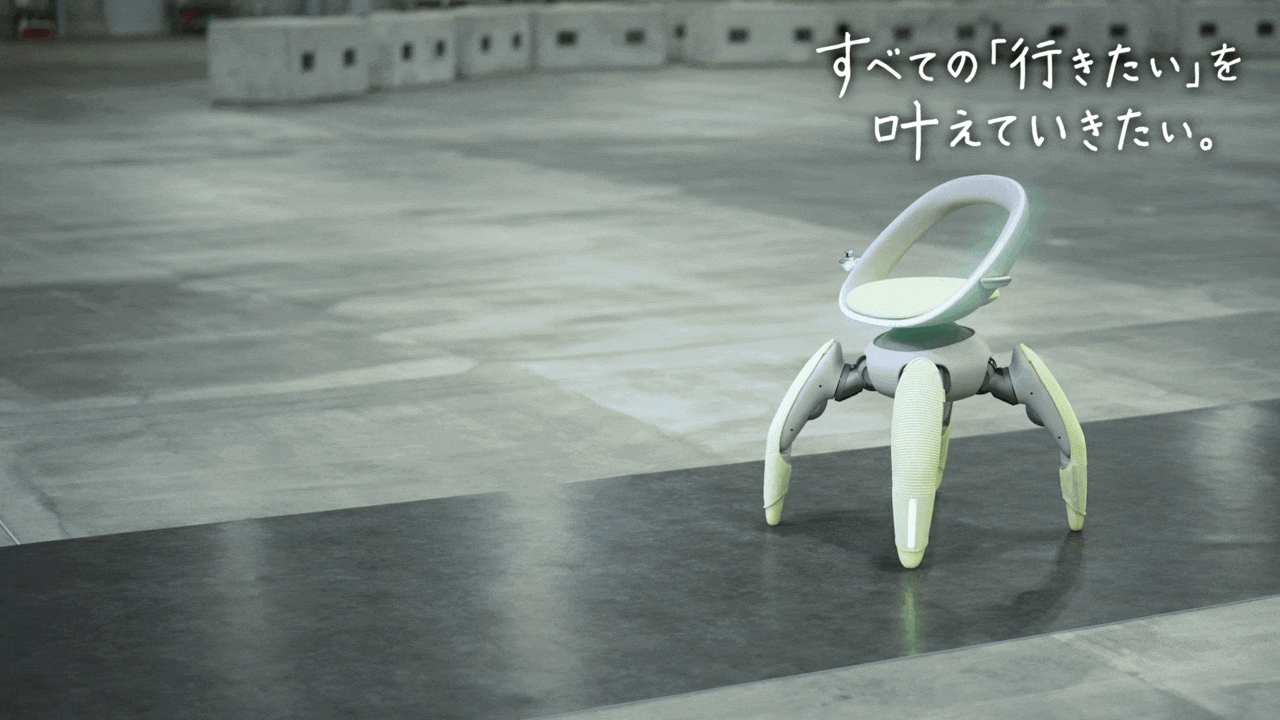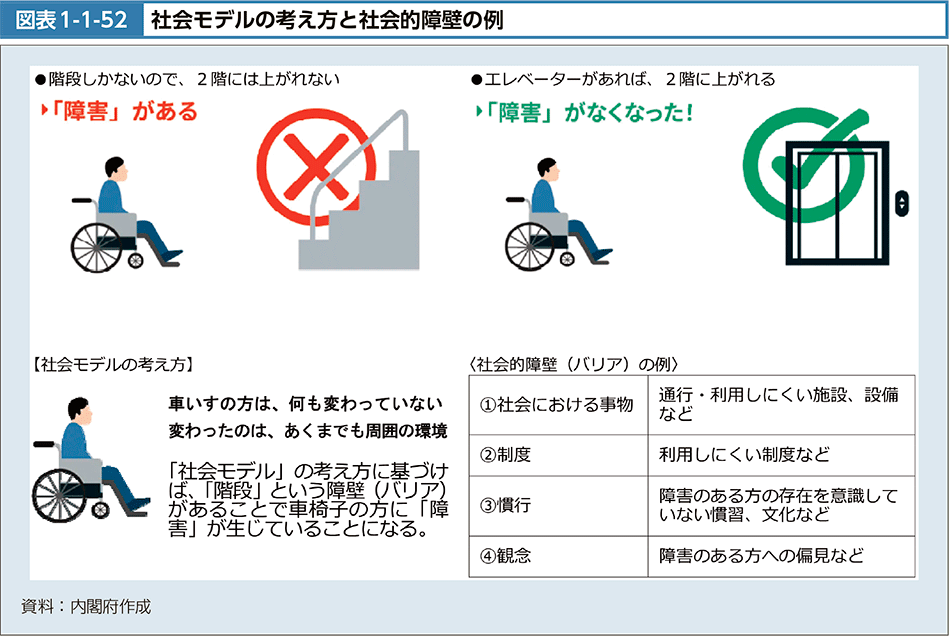トヨタNews

えっ!モビリティが自分の可能性を無限に拡張!?どういうこと?
「なにこれ、かわいい!」「こっちはめちゃくちゃカッコいい!」
これらのモビリティ、いったい何者!?
話を聞くと内容がすごかった!まさか、こんなものをこっそり開発していたとは…
今回は、およそ7,000字もの長文記事。前半は3つの驚きのモビリティ(試作品)をご紹介。後半は「障害」への考え方が大きく変わるかもしれない内容だ。
きっと「読んでよかった!」と思っていただけるはず。逆に、知っておかないと誰かに誤解を与えてしまうかも…?
ありそうでなかった!誰もが楽しめるモビリティ
10月30日(木)~11月9日(日)にて開催されているJapan Mobility Show 2025。トヨタブースのコンセプトは「TO YOU」。
誰かを思い、一人の“あなた”を見て、どうしたら喜んでもらえるかを考える。「あなた目掛けて」という一心で開発されたモビリティが展示されている。
そこには、新シリーズ「me(ミー)」の3モデルも初登場。障害の有無や年齢に関係なく、みんなが一緒に楽しめるシリーズだ。あなたがつくる未来の真ん中には、クルマがあって、たくさんの笑顔があってほしいという願いが込められている。
先進デザイン開発室 渡部卓也 主任
「すべての『行きたい』を叶えていきたい」という想いで開発しました。meのネーミングの由来は、自分 (me)の可能性を無限に拡張する、という意味です。
活気があってスポーティなイエローで統一。みんながもっと自由に、そしてダイナミックに。まだプロトタイプですが今後、さらに進化させていきます。
まずは、walk me(ウォークミー)を紹介
コンセプトは「車いすのひとつ先へ」。
車いすと違ってタイヤではないので、段差を気にせず、屋内から屋外までをシームレスに移動できる4足歩行モビリティだ。正座から起き上がるような日本的な動きも取り入れたという。
先進デザイン開発室 河田美紗子(左)西村隆 主任(右)
車いすでは回転が難しいような、室内の狭い場所でも自由に動けます。段差をのぼれるので座ったまま階段で2階に行ったり、外のクルマにもそのまま乗り込める。まさにバリアをなくすモビリティです。
将来的にはジャンプしたり、声の指示で各モビリティと連携して好きな場所に自由に行ける世の中を目指しています。
今までの歩行ロボは、どこに足を出すかを計算で導いていたがwalk meはまったく違う。約1万台の動作シミュレーションから良い動きを覚え、日々進化していくという。
次に、スポーツに特化したboost me(ブーストミー)
こちらは、重心移動だけで動けるモビリティ。
手を自由に使えるので、バスケやテニスなど車いすスポーツの間口を広げることを目指している。障害の有無に関わらず誰もが同じ土俵でプレーできるようになれば画期的だ。
先進デザイン開発室 石塚聖吾(左)梅子洵 主任(中)齊藤匠紀(右)
テクノロジーの進化でパラアスリートの成績が上がったりするように、すべての人に、自分の能力が拡張する体験をお届けしたいと思ったんです。
座面は、乗る人の体型にフィットする必要があるので3Dプリンターで製作。シート部分を着脱可能にすれば、本体はレンタルして低額で遊べる工夫も検討中です。
最後は、アウトドアを想定したchallenge me(チャレンジミー)
障害の有無に関わらず、誰もが究極の冒険を楽しめる電動車いすだ。
グリップを握ることで体を支え、ジョイスティックで操作。車いす版のランドクルーザーのようにも思える。
先進デザイン開発室 梅子洵 主任(左)石塚聖吾(右)
シニアから車いすユーザーまで、誰もがハイキングや釣り、オフロード走行などアウトドアを好きなだけ楽しめます。筒状のアームレストにバッテリーや制御装置を配し、防水性も確保しました。
誰もが自分らしく、好きな場所へ。アウトドアをあきらめていた人たちに新たな幸せを届ける可能性に満ちたモビリティだ。
すべての「行きたい」を叶えていきたい。そこには、障害のある方の移動も当然含まれているのだが、この記事では「障がい」ではなく「障害」と記載している。
トヨタでは2025年11月から「障がい」を「障害」と漢字で表記することにしたのだ。なぜか―
「障害」と表記する想い
まずはこの図を見ていただきたい。障害はその人の問題ではなく、周囲の環境など社会側にあるという「障害の社会モデル」の考え方だ。
出展元:令和6年度版厚生労働白書 たとえば車いすで移動中、階段しかない場面に出くわす。それまではバリアを感じずに移動できていたのに、周囲の環境によって障害が発生してしまう。
この場合、エレベーターを設置すれば障害はなくなる。
「障害はその人の問題」という視点だと、リハビリなどで本人が解決するしかなく、解決できない問題も多い。多様性が重視される時代にそぐわないともいえる。
だが「障害は、環境など社会の仕組みが合わさって発生している」という視点だと、世の中の障害をみんなでなくしていける。インクルーシブな世の中へ大きな可能性が生まれるのだ。
トヨタでは、これまで「障がい」という表記も使われていた。それは、その人に害はないという考えに基づいている。
その考えは決して変わるものではない。だが個人の尊重がより重視される時代、社会に存在するさまざまな“壁”こそが障害になっていることを、みんなで意識的に理解するためにも「害」と漢字表記にするのだ。
いちばんの目的は「表記変更」ではなく「意識変革」。
誰もが成長を実感し、働きがいを持って人生を豊かにする「全員活躍」を目指すトヨタ。だからこそ、言葉を見直すことで、意識を変え、行動を変え、そして社会を変えていく大事な一歩にしようとしたのだ。
当事者たちはどう感じているか
とはいえ、当事者たちはどう感じているのか。トヨタに加え、 障害のある人の雇用の輪を広げる特例子会社のトヨタループスで働く人たちに集まってもらい本音を聞いてみた。
考え方は人それぞれなので意見は二分するかと思われた。しかし、語られた本音はほぼ同じような内容だった。当事者たちも「想いは同じだったんだ!」と驚きの声を上げる結果に。
- 表記はどちらでもいい。特に気にしていない
- 当事者を置き去りにして、周囲の人たちが表記の議論をしていると感じる
- 漢字にすることで「障害」について考えるキッカケになれば嬉しい
- 大事なのは表記よりも、みんなが話し合って実際にバリアがなくなること
- 会社などで障害について考える教育こそが大事
それぞれの声を紹介していく。
①「障がい」と「障害」の表記についてどう感じるか
トヨタ自動車 植田
表記はどちらでもいい。それよりも、この論争をしている人たちに「当事者はどれくらい含まれているのだろう」と思ったんです。当事者の気持ちを置き去りにされている気がして…。でも表記変更によって「障害」について考える機会が生まれるのはいいことだと思います。
トヨタ自動車 大野
私もどちらでもいいと思いました。それよりもSNSの表記論争を見て「怖いな」と思ったんです。正解はないのに、どちらかが悪者扱いされる。バッシングを受けた人は障害について考えることを恐れてしまうと思ったんです。
当事者からすれば、表記よりも、住みやすい環境や制度をみんなで話し合うことが大事。
子どものころ「障害者!」と、ふざけて言い合っている人を見て、自分に向けられた言葉ではなくても、悲しくて泣いたことがありました。なにが「害」なのか、情報を届ける機会が増えればいいなと期待しています。
トヨタ自動車 瀧口
私は表記を意識したことがない。身体障害者手帳の「害」の字を見慣れているからですかね。でも社会に害があって、個人に否はないというなら「障害者」にしてしまうと個人に紐づく気もします。大事なのは表記よりも、実際にある壁をなくしていくことかなと思いました。
トヨタ自動車 佐藤
僕もどっちでもいいです。海外で、障害のある人のことをDisabledと書いてあっても違和感がなかったので。当たり障りのない平仮名にして「配慮してますよ」というポーズを示すよりも、実際にしっかり配慮していくことが大事だと思います。
ちなみに英語では「健常者」という言葉はないそうだ。
トヨタループス 西水流
僕は、障害者の「害」に悪いイメージがありました。自分が“障害者”になったとき、まわりから白い目で見られたので、自分に害があると思ってしまったんです。
でも、トヨタループスに入社して「害」ではなく「壁」だと考えるようになり、表記はどちらでもいいと思うようになりました。漢字にするならば、どうして漢字にするのかしっかり説明されるといいですね。
トヨタループス 早川
多くの企業が平仮名にしているので、漢字にすると聞いて、世間と逆のことをするんだと思いました。でも、理解を深めるためなら漢字にしてもいいのかなと感じます。
トヨタループス 森川
自分が障害者になっときに「害」の意味を考えたことがあって。行きついた結論は「できないことや苦手なことがある」ということ。でもそれって健常者も同じ。
障害者手帳には思いっきり「害」の字が使われているんです。社会サービスを受けるときにはこれを出すんですが、心の中でみなさんにもできないことありますよね?と問いかけながら出しています。
すると、ふっと表情が和らぐ人がいたり、なんとも言えないような顔をする人もいる。そこを観察するようにしています。なので、僕は漢字でいいと思っています。自分から世の中に問いかけることができるので。
トヨタループス 外輪
表記はどちらでもいいです。私は生まれつきなので、障害があるというよりも「こういうことができない」と思っている部分が強くて。自分のことを障害者だと意識していない。本来は区別すること自体がおかしいですよね。
話を聞くと、表記については周囲の人たちが過剰に言い争いすぎているようにも感じられた。肝心なのは表記よりも、世の中のバリアを着実になくしていくことなのだ。
しかし、漢字表記について家族からは「嫌だな」という声もあったという。
トヨタ自動車 植田
家族に「害」を漢字にするかもしれないと話したら「嫌だな」と言っていました。普段から周囲で支えているからこそ傷つく表現なのかもしれません。そういう意味でも、なぜ漢字にしたのかを丁寧に伝えることが大事だと感じます。
トヨタ自動車 大野
家族は、当事者とは違った苦労もあると思っていて。でもそんな家族も表記のことより、もっと住みやすい環境になってほしいと願っていると思います。
私は車いすユーザーですが、友だちと行ったお店に段差があって入れないことがあって…。そのとき「あなたが悪いんじゃなくて、建物が悪いから気にしないで次の店に行こう!」と言ってくれたんです。その子は、漢字表記を喜んでくれると思います。
②「障がい」と平仮名になった当時はどう思ったか
今から20年ほど昔、漢字から平仮名に変わっていった当時のことも聞いてみた。
トヨタループス 外輪
社会がここまで考えてくれるようになったんだ!と思いました。
トヨタ自動車 佐藤
僕はまだ中学生でしたが、平仮名になったことで触れてはいけない存在になったように感じました。障害者は「配慮しなくてはいけないもの」。腫れ物に触るようなネガティブな印象を受けました。
平仮名はどうしても“つくられた言葉”と感じる。そんな声もあった。
③正しい配慮とは何か?
相手を思いやる配慮。しかし配慮が可能性を制限してしまうこともあるという。
トヨタ自動車 植田
みなさんどう接していいか一生懸命考えてくださっていると感じます。それ故に「大丈夫です」と言っても「本当に大丈夫?本当に?」と何度も聞かれることがあって。配慮されすぎると、その人の可能性を縮めてしまう可能性もあるんです。
トヨタ自動車 大野
「障害があるから出張に行くのは難しい」と勝手に判断されないか不安でした。でも「出張に行ってみる?」とまずは相談ベースで聞いてくれたのが嬉しかったです。他人は障害のことを触れづらい。だからこそ自分がどこまで配慮してほしいかを伝える。私たちからの配慮も大事だと気づけた瞬間でした。
トヨタループス 谷口
「手伝おうか」と言われると、ありがたい反面、断りづらさもあります。長く一緒に働いている人は、どこまでできるのかを理解してくれるので、やっぱりコミュニケーションが大事だなと思います。
トヨタループス 外輪
誤解されがちですが、補聴器をつけていても全部が聴こえるわけではないんです。私は口の動きで言葉を理解することも多い。だから耳元で大きい声でしゃべられると「違う違う(笑)!口を見せて」ってなるんです。
聴覚障害といっても一人ひとり違いがあって、口の動きで言葉を理解する人もいれば、手話のみでコミュニケーションをとる人もいる。まずは相手を知ることが大事ですよね。
トヨタループス 早川
私の障害は見た目で理解してもらえないので苦しみもあります。てんかんで、いつ倒れてしまうかわからない。でも事前に同僚にはその話をしているので、職場のみなさんが気にかけてくれています。
トヨタ自動車 佐藤
僕は義足を使っていて、個人的に不便なことはほとんどない。長ズボンだと気付かれないことも多い。でも仕事で「朝からずっとイベント対応」となると大変なことも。見た目では分からないので、自分で主張をすることも大事だと感じました。
トヨタ自動車 瀧口
まずはその人の症状を知ってもらえると嬉しいです。僕は日々の体調によって体の変化もある。今日は転びそうだなとか、エレベーターを待つのがしんどいときもあります。
エレベーターを待つ間、私を含めて椅子に座りたい人もいると思います。一方で、椅子が多すぎると邪魔になるし、多くの人は椅子を必要としない。そのジレンマはありますね。
トヨタ自動車 佐藤
今の社会は「健常者が暮らしやすいように」つくられているように、マイノリティのことを決めるのはマジョリティ。どうしても多数派の意見が強い。だからこそ、マジョリティとマイノリティの密な会話が大事だと感じます。
障害の有無に関わらず、一人ひとりみんな違う。だからこそお互いが理解しあうことが大切なのだ。
次の最終ページでは悲しい実話も出てくる。このようなことが起こらないために、当事者たちはあることが必要だと口を揃えた。その内容とは…
④障害への理解を深めるために何が必要か?
車いすで電車やバスに乗ると「邪魔だ」と言われることもあるそうだ。
トヨタループス 森川
電車に乗ると、欧米の方はさっと席を譲ってくれるんです。日本人は照れくさいのか「どうぞ」とならないことが多い。教育の差があるかもしれません。海外では障害がある方も堂々とされていることが多い。この差は敵わないなと思いました。
トヨタ自動車 植田
先日ジムに行こうと家を出たら、私より背が大きい子どもたちに囲まれて、身長を馬鹿にされたんです。また同じように囲まれるんじゃないか、もしかしたら暴力を振るわれるかもと思うと、ジムに行くのが怖くなって…。私も教育の重要性を感じました。
トヨタループス 外輪
昔、娘が保育園に通っていたとき、娘の友だちが私の補聴器を指さして「それなに?」と聞いてきたんです。それが嬉しくて「耳が聞こえないから、聞こえるようにするものだよ」って言うと「へー!」って素直に受け入れてくれて。
でも、親御さんたちは「そんなこと聞いちゃダメ」って…。私は聞いてくれたほうがありがたいのに。
家に帰って「友だちにお母さんの耳のこと聞かれる?」って確認したら「よく聞かれるよ!」って。なんて答えるのと聞いたら「うちのお母さんは普通に喋るから全然困ってないよ」と。
それを聞いたとき、すごく感動したんです。やっぱり小学生など、頭が柔らかいときに障害について学ぶ機会があったほうが自然に受け入れられるのかもしれません。
世の中には「障害のある人への接し方が分からない」と距離を取る人もいるのが実態だ。だが、そういう意識こそがバリアのない社会を遠ざけてしまう。
読者のみなさんも、上司や部下、友人とコミュニケーションをとる際は、相手の気持ちを考えて接しているだろう。分からない場合は直接会話して、その人の働きやすさや可能性を一緒に考える。それは障害の有無に関係なく同じはずだ。
今回は約7,000文字の長文記事。ここまで読んでいる方はきっと少数。今ここを読んでいるあなたは「障害とは何か」「当事者の本音はどうか」を知ろうとする優しさを持っている人に違いない。
だからこそお伝えしたいことがあります。どうか「障害とは何か」、近くの人たちに投げかけてくれないでしょうか?
可能性を信じて一歩一歩前へ進もうとする人がいる。
その人たちに、壁をつくってしまう人になるか。一緒に壁を壊していく人になるか。
最後まで読んでくださったみなさんは、きっと後者になっているだろう。