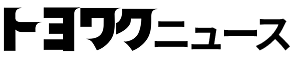トヨタNews

トヨタ生産方式で「小学校の働き方」を改善すると、まさかの結果に!
小学校で授業を受けているのは、子どもたち、ではなく先生!?
近年、社会問題にもなっている教師の長時間労働。働き方改革を目指して、福岡県のある小学校ではトヨタ生産方式(以後TPS)を取り入れているという。
果たしてクルマづくりで培ってきた技は、学校でも通用するのか…?
トヨタから先生たちへ難問
いきなりですが、読者のみなさんに問題です。
この表の1〜50の数字を順に数えた場合、何秒かかりますか?
これは、法則を見つけることで作業をラクにするトレーニング。答えは後で紹介するが、あることに気づけば一気に時短できるのだ。それは仕事でも同じ。
トヨタ自動車九州 TPS推進室 熊田浩グループ長
先生たちは、行事の準備、経理処理など多数の作業に追われています。だからこそムダをなくす法則を知り、仕事をラクにすることが重要。そうすれば子どもたちと向き合う時間も増やせるはずです。
ちなみに、先ほどの答えはこうだ。
4つのエリアに分けると、左上→右上→左下→右下と数字が順番に割り振られている。この法則を知れば大きく時短が可能だ。
今回取材したのは福岡県宗像市の赤間西小学校。働き方改革のモデル校として、昨年の夏からトヨタ自動車九州のメンバーが現場に入り込み、先生たちと一緒にTPSの実践に取り組んでいる。
宗像市教育委員会の小森琢馬係長は「民間の力を借りて、学校の働き方改革を違う視点で推し進めたかった」
「市としても、水泳授業の指導を民間に委託するなど業務改革を進めていますが、外部目線で見たときに、どこに課題があると感じ、どう改善するかを知りたかった」と語る。
学校側からはこんな声も。
宗像市立赤間西小学校 川上文香教頭
教育現場にムダなことは1つもない。そう思っていました。ただ、トヨタさんからアドバイスをもらうなかで、視点を変えるとムダがあったんだと気づかされたんです。新しい視点で見ることの重要性を学べました。
どうなる!?「だるま問題」
月に1度、トヨタ自動車九州の担当者が学校を訪問。取材したこの日、議題に上がっていたのは体育準備室の使い方だ。そこで起こっていた「だるま問題」とは…。
この巨大だるま、年に1度の運動会でしか使われない。にも関わらずモノが溢れる体育準備室では手前にしか置くスペースがない…。その結果、よく使う他の用具が取り出しにくくなっていた。
トヨタ自動車九州 TPS推進室 佐々木重博シニアエキスパート
屋外の倉庫に移動しませんか?と相談しました。でも先生たちは反対されたんです。「地域の人がつくってくれた大切なダルマなので、劣化しやすい屋外には置きたくない」という理由でした。
そこで先生たちが話し合って、体育準備室を整理し、置き場所を探すことになったんです。トヨタ側はあくまで提案するだけで、決めるのは先生たちです。
改善は、一過性ではなく定着することが重要だ。
そのため学校側に改善意識が根付くように、トヨタはあくまで提案や相談のスタンスを取っているという。いわば、土壌づくりのサポートだ。
そして体育準備室の大掃除がスタート。紅白のだるま兄弟は、掃除が終わるまで廊下で待機。本当にスペースが生まれるのか不安そうな顔をしていた。
掃除中に我々が「これ何ですか?」と聞くと、先生も「何ですかねコレ…」と使い道がわからないものも…。本当に必要か、置き場所は適切か、先生たちが自分たちで判断。
どこに何があるか瞬時に分かるように、トヨタの現場のように“かんばん”のようなシールも 掃除が終わると奥側にスペースが生まれ、問題も解決!部屋がキレイになるだけではなく、使いやすくもなった。
先生たちは、忙しくてモノを整理する時間を確保できなかったという。だが、忙しいからこそ、モノの置き場を決めてルールをつくったほうが、全員のムダな時間はなくせるのだ。
次のページでは、みなさんの職場でも参考になるヒントが多数。是非マネしてみませんか?
改善事例が続々と!
去年の夏から1年かけ、あらゆるTPSが実践された。代表的な4つを紹介する。
事例① 放送室のケーブルを見える化
【改善前】
あらゆる種類のケーブルが一緒に置かれ、何に使うものか担当教員しかわからない
▼
【改善後】
ケーブルごとに、場所と用途を明記。誰が見てもすぐにわかる
紙の色を変えることで、ケーブルごとの違いが一目瞭然!探す時間はもちろん、片づける時間も大幅に削減できた。
事例② 放送室のモノの置き場所を決める
【改善前】
あらゆるモノが無造作に置かれ、探す時間がかかり、紛失しても気づかない
▼
【改善後】
置き場所を決めたことで、探す時間がかからない。見た目もキレイに
事例③ 会計処理をまとめて効率UP
【改善前】
各担任の先生が、放課後に会計処理をしていて帰宅時間が遅くなっていた
▼
【改善後】
学年ごとに会計係を1人配置。各先生の負担が減少
学校では、会社のように経理や総務の部署がないことが多い。夕方に授業が終わってから会議や事務作業が続くので、どうしても終業時間が遅くなりがちだったのだ。
事例④ カギ利用者も見える化
【改善前】
各教室のカギを、誰が持ち出したのかわからない
▼
【改善後】
カギを持ち出すとき、マグネットを貼ることで、誰が使用しているか明確に
カギの利用者を見える化した件は、先生たちが自主的に考えたそうだ。まさに改善が定着しつつある証。先生たちはこのようなメモも持ち歩いている。
なぜそんなことをするの?
TPSの取り組みについて、先生たちの本音を聞いてみると…
最初は「忙しいのになぜそんなことするの?」と不満でした(笑)
でも、どこに何があるか新任の先生でも一目瞭然になったので「ラクだな~」と実感できるようになったんです。
「めんどくさいな」と思うこともありました(笑)ただやってみると、本当に手間が省けて「やってよかった」と心から思えます。
はじめは理解されなかった。それはトヨタ側も感じていたようで…
トヨタ自動車九州TPS推進室 和久田篤男主幹
はじめは「学校現場を知らない人たちが何を言ってるの?」という感じもあったと思います。だからこそ、やり方を押し付けるのではなく、現場で困りごとを聞く。
先生たちは長時間労働をしているという認識が薄かった。私たちが伝えたかったのは「先生、もっとラクしませんか?」ということです。小さい改善を繰り返すことで、少しずつお役に立てればと思います。
トヨタが大切にしているのは、ただムダを省くことではなく「誰かのために」という想いだ。校長先生は「意外だった」と語る。
宗像市立赤間西小学校 高橋茂校長
トヨタさんからは「現場のムダをなくそう」と言われると思っていたのですが「どんな学校にしたいか」「どういう先生でありたいか」を問われて驚きました。
トヨタの「誰かのために」という考え方は、我々にとっては「児童のため」そして「先生自身のため」と言い換えることができ、どんな場所でも通ずる考え方だなと感じました。
忙しくても子どもたちと向き合う時間は、先生たちにとってかけがえのない時間なのだ 先生という仕事は“個人商店”。それぞれが自分流のやり方を持っている。だからこそムダをなくす共通のルールをつくれば、全員の仕事がラクになっていく。
効率化が目的だと誤解されがちなTPS。豊田章男が「私の解釈ですけど」と語った"トヨタ生産方式" 豊田章男の解釈という記事も必見だ。
宗像市では別の小学校でもTPSの取り組みを始めるという。また、この学校でTPSを体感した先生たちも、いずれ別の学校に異動する。異動先でもTPSの思想は広がっていくだろう。
学校での働き方は、劇的には変わらないかもしれない。だが、TPSの意識を持つ人が少しずつ増えることで、着実に未来は変わっていくはずだ。