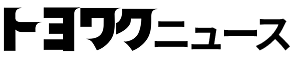トヨタNews

これがトヨタのからくり! 進化し続ける「インパネ意匠シューター」
「一時置き場は部品であふれ、AGV(部品などを所定の場所に運ぶ無人搬送車)は渋滞。これではリズミカルに作業できない…」。
元町工場 第1組立課が担当する、インパネ意匠取り付け現場では技能員の不満が溜まっていた。
それは、多品種少量・特殊生産のモノづくりに挑む元町工場ならではの問題だった。
「ここでは9車種のインパネ意匠を取り付けています。同じ車種でもグレードによって部品が変わるので、必然的に部品点数が多くなり、一時置き場があふれていました」。
そう語るのは、第1組立課2NB組SXの永山栄二。
リズミカルに作業ができないのは、頻繁にやってくる部品運搬車がAGVの動線に侵入し、自動停止してしまうからでもあった。
写真左:奥の緑色のものが部品運搬車、手前の台車下の青いものがAGV(部品などを所定の場所に運ぶ無人搬送車)。 写真右:AGVが完成インパネAssy(インパネに必要なメーター、スイッチ、配線、カバーなどの部品が全て組み付けられたもの)を運送しているところ
それらの課題は、現場の技能員のみならず、新しい車種を立ち上げる生準(生産準備)グループにとっても悩みの種だったという。
工程の見直しから生まれた「インパネ意匠シューター」
第1組立課2NB組SX 永山栄二
具体的にこういうモノが欲しいと決まればアイデアは出てきます。
しかし、今回はどんなレイアウトで、どういうモノを設置して、どう取り回すのかを考えるところから始める必要がありました。そこが一番大変でした。従来は作業台の中に部品棚があり、生産指示情報に従いながら必要なパーツを取り出して組み立てていた。しかし、その工程をイチからすべて見直し、必要な部品がトレイに載せられた状態で流れてくるように変更した。
改善後の作業台からインパネを持ち上げるようす。トレイの黄色枠内に、さまざまな種類のインパネや部品がキレイに納まっていた
では、部品が載ったトレイをいかに効率的に受け取り、返却するのか?
そこで生まれたのが、今回紹介するインパネ意匠シューター。ここで実物の動画をご覧いただきたい。
全ての部品を取り付けたあと、空のトレイを軽く押しだすと、自重によりトレイは下段に滑り落ちていく。すると、自動で上段のストッパーが外れ、次の部品が載ったトレイが流れきて定位置にセットされる
写真左:空になったトレイを押し出す永山。 写真右:永山の後ろでは技能員が部品の組付けを行っていた
この仕組みには動力が一切使われておらず、「からくり」によって制御されている。
トヨタにおける「からくり」とは、歯車やテコの原理、バネなどの簡単な機構を使い、動力を使わずに作業を自働化し、改善する仕組みのことだ。トヨタイムズではこちらの過去記事でも多くの事例を紹介している。
シューターの完成前は、別の場所にあった順立てエリア*¹から意匠準備工程エリアまで、部品をAGVに載せて運搬していたという。しかし、工場内は部品運搬車が頻繁に行き交っており、部品供給作業中には狭い通路上で停止するため、AGVの待機が発生。待機解消後にAGVが順立て部品*²を供給していたため、技能員の手待ちが発生することもあった。
*¹自動車部品を車両の組立順序に合わせて1台分の必要な部品を順序立てする場所
*²車両の組順序に合わせて1台分ずつ順序立てされた部品そのため、前後工程も含めて工程をすべて見直し、モノの流れやレイアウトを大きく変更する中で、インパネ意匠シューターを設置した。結果的にAGVを使用する必要もなくなり、渋滞問題も解消できたという。
シューターの完成当初、新しいトレイが流れてくる上段のストッパーは、技能員が手動でレバーを下げて解除する仕組みだった。しかし、さらなる創意くふうにより、作業を終えたトレイを押し出すだけで自動解除される仕組みへと改善された。まさに「改善後は改善前」の言葉どおりだ。
写真中央に見える三角形のものが上段のストッパー
空になったトレイが下段に流れていくと、上段のストッパーが解除される
その際に活用されたのは、まぐろ漁で使われる太い釣り糸。キャスターの付いたラックの上下運動と、ウエイトの働きを連動させることで、ストッパーの解除を実現させている。
青色の糸が、まぐろ漁で使われる太い釣り糸だという。ストッパーにしっかりと結ばれていた
トレイの自重により下がった左側のレールと連動して、左下のキャスター付ラックが屈折。その動きと右側のウエイトの働きを釣り糸で連動させ、ストッパーが解除される仕組み
永山
トレイを戻す場所と解除レバーには少し距離があったため、技能員が少しでも無駄なく動けるよう、そこも自働化しようと思いました。ウエイトの重さ調整には、かなり苦労しました。
最先端のモノづくりこそ、からくりが必要不可欠
永山の部署は、各職場から改善依頼のあったモノを製作するのが主な業務。その他、多様化の時代に向け、あらゆる人が働きやすい職場環境の評価や改善、工場内の安全整備も担当している。
BEVなど最新のクルマをつくる工場は、大きな機材をモーターなどで動力制御しているイメージがあるかもしれない。しかし、最新だからこそ、からくりを活用することが求められるという。
永山
第一組立課では、なるべく動力を使わない方針です。というのも、他の車両工場と比べて工程変更の頻度が高いんです。
その際、各種配線を取り外して移動、そこから新たに取付け作業となると、一日で終わらないこともある。一方、無動力のからくりであれば、設備の移動がすぐにできます。
からくりを使った改善は、CO2を排出しないため、脱炭素視点でも注目されている。
多様性の時代において、創意くふうはますます重要になる
永山
賞金は、シューターで1万円、ストッパーの自動解除で1万円になりました。でも、今回私は提案には参加せず、実際に手を動かしてからくりを製作したメンバーに提出してもらいました。
みんなで意見を出し合って、それが形になったことが嬉しかったです。現場の技能員からも“ラクになりました”という言葉を聞いて、本当に良かったなと思いました。
自分はあくまで調整役だからと謙遜するが、この改善が実現したことは大きな喜びだったという。若手時代は義務として創意くふうを提出していたが、その思いは徐々に変化していった。
永山
創意くふうのレベルが上がるにつれ、誰かのためにという考え方に変わっていきました。
また、これまでは作業を見て覚えるという風潮がありましたが、多様化の時代においては、どんな人でもわかりやすくスムーズに作業できる環境づくりが不可欠です。その実現のためにも、創意くふうは必要だと感じています。
最後に「改善とは何か?」を聞いてみた。
「継続することで力になっていくものだと思います。提案し続けるだけではなく、一度改善したものを進化させ続けるということも大事だと思っています」。
<関連リンク>